轟 夕起夫:映画短評の著者

略歴
文筆稼業。1963年東京都生まれ。「キネマ旬報」「月刊スカパー!」「DVD&動画配信でーた」「シネマスクエア」などで執筆中。近著(編著・執筆協力)に、『伝説の映画美術監督たち×種田陽平』(スペースシャワーブックス)、『寅さん語録』(ぴあ)、『冒険監督』(ぱる出版)など。
近況
またもやボチボチと。よろしくお願いいたします。
リンク
映画短評一覧

ブラックフォン 2
マニアックで終わらずに、楽しくヤバさを加速させている
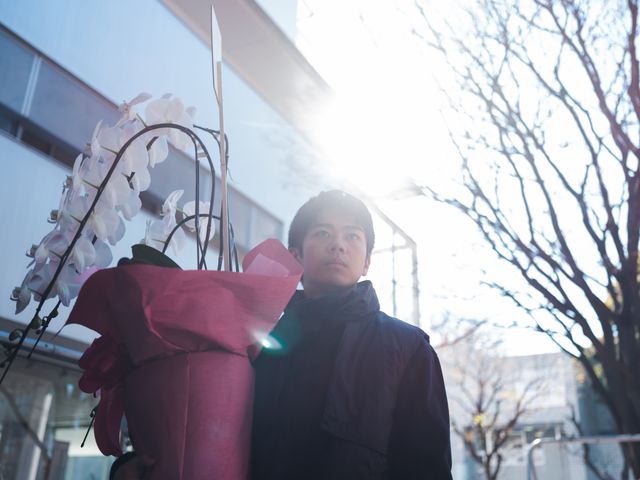
見はらし世代
見はらすしかない視線、見はらすしかない世代

てっぺんの向こうにあなたがいる
のんと吉永小百合の“二人一役”を実現させた製作陣に拍手!

さよならはスローボールで
“透明ランナー”の如き共同幻想が立ち上がってくる

ふつうの子ども
今年の自分の「邦画ベスト・テン」にランクイン!

海辺へ行く道
目指すは、映画ならではの“自由”と“衝撃”の心地よさ!

愛はステロイド
DEAD OR ALIVE な、愛の副作用の行方

キムズビデオ
アクティビストな監督たちのタガが外れた行動に気圧される

「桐島です」
「何かの間違いで主人公となってしまった」男

黒川の女たち
『秋刀魚の味』の、あの名台詞と似た言葉が出てくる意味

MELT メルト
金田一のいないベルギー版『本陣殺人事件』(青春残酷篇)

F1(R)/エフワン
サウンドデザインが引っ張り、全身が“耳”となる!

国宝
人ならざる結界へと手を伸ばす“人非人”ゆえの流離譚

劇場版 それでも俺は、妻としたい
センシティブなテーマを扱ったスクリューボール・コメディかも

秋が来るとき
人智では計り知れないことがミステリー

ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング
どーした? トム&マッカリー!

サブスタンス
クリーチャー化する女性スターの悲劇と屈折した多幸感

青春 -帰-
ある世代の人々の青春時代を歴史的に捉える冒険的な試み

青春 -苦-
人物それぞれの体温や息遣いがヒシヒシと伝わってくる

異端者の家
折伏オヤジがゴリゴリの支配欲を剥き出しにしてゆく怖さ!


