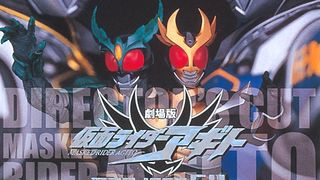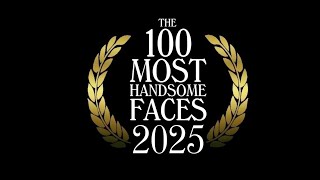ガール・ウィズ・ニードル (2024):映画短評

ライター4人の平均評価: 4
毒気と悪夢に覆われた映像だけで観る価値アリ
初期L・フォン・トリアーのエッセンスに、これまた初期のD・リンチの風味を少々。デンマークの黒歴史を描き出すうえで、この試みはうまく機能している。
冒頭から顔面歪みの悪夢的なモノクロ映像が叩きつけられ、第一次大戦後の悪夢に誘われる。この“悪夢”は連続殺人よりも、貧困の要素が濃い。家賃も払えないヒロインの苦境。必死のあまり彼女はイヤな人間にもなるが、それが殺人鬼の暗躍につながっている点が面白い。
社会の恐怖に目をつぶることの意味を問うたという監督の発言は納得。とはいえ印象に残るのは社会性よりも毒気と映像で、『ヨーロッパ』プラス『エレファントマン』の趣。監督の次の作品が楽しみになる。
時代ものだが今の社会についても考えさせる傑作
無慈悲で、残酷で、冷たい物語が、黒と白の強いコントラストが強烈な古い写真のような映像で、淡々と語られていく。そのじわじわとした恐ろしさに、心をつかまれっぱなし。実在した連続殺人事件にもとづくが、犯人ではなく、その背後にあった社会の実態に焦点を当てるところが、今作をより意義深く、興味深くする。主人公の女性は、工場で働く、ごく普通の女性。天使のような心は持たないが、それは私たちも同じ。ただ生き延びようと必死の彼女に、ほかに何ができたのか。ここで描かれる社会は女性だけでなく、負傷した帰還兵や、持たざる者にも厳しい。時代ものではあるが、現代は果たしてどれだけ進歩したのかも考えさせる、奥深い傑作。
荒廃した社会と人間の行動学について
戦争と貧困は我々に何をもたらすのか。第一次世界大戦が終わってすぐのコペンハーゲンを舞台に、お針子の女性カロリーネの受難が物語の主軸となる。家賃も支払えぬ困窮と望まぬ妊娠。戦死したと思っていた夫は顔に仮面をつけて帰ってくる。実話ベースながら怪奇寓話の趣があり、サーカスという要素、ミハウ・ディメク撮影によるモノクローム映像などD・リンチ監督の『エレファント・マン』等にも通じる雰囲気がある。
やがてカロリーネが出会うダウマという女性――当時は犯罪として裁かれた彼女の行動は本当に残忍なものだったのか。その正当性についての再検討が我々の責務だ。M・リー監督の『ヴェラ・ドレイク』にも補助線を引きたい。
行為の醜さ、映像の美しさ、その対比が鮮烈
冒頭、登場人物たちの顔が並び、顔に浮かぶ気配が、ライティングの変化によってさまざまに変貌していく。この光景が物語を象徴している。誰もがそこで生き続けようとするだけで、善人にも悪人にもなってしまう。主要登場人物たちは女性だが、女性を描く映画ではなく、人間の物語が紡がれていく。
第一次世界大戦直後のデンマーク、実話を下敷きに、貧困から抜け出そうとあがく若い女性が、やがて異様な状況に陥るさまを描くが、モノクロ映像の美しさと、映し出される人間たちの行為の醜さ残酷さ、その対比が鮮烈。黒が強く湿度の高い滑らかな映像は、ロバの目に映る世界を描いた『EO イーオー』のミハウ・ディメクが手がけている。