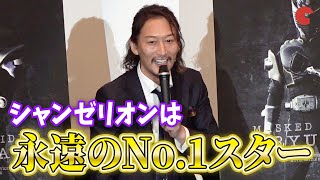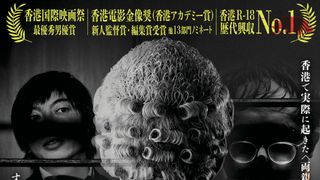終わりの鳥 (2024):映画短評

ライター3人の平均評価: 4
私(たち)にとっての“Good Day”とは
ポップで人懐っこい「死」のヴィジョンが秀逸。いかにもA24的なクリーチャーでもあるが、残酷な運命を告げられた15歳のチュースデーは、この死神=赤い鳥とむしろ親密な絆を結ぶのだ。彼女を演じる『恋人はアンバー』のローラ・ペティクルーが見事。そして物語は娘の死を受容せねばならない母親へと力点を移していく。
死の悲しみは当人ではなく、遺された他者が感じ取るもの――これは古代ギリシャの哲学者エピクロスが説いた死生観に基づくものだろう。テーマ曲的に使用されているのがアイス・キューブの“It Was a Good Day”。92年、ロス暴動のすぐあとに発表された名曲の意味合いを絶妙にスライドさせている。
その死神は、なんだかイイやつだった!?
死神的な存在として描かれる鳥のキャラが、まず面白い。哲学者のような言葉を吐き、体のサイズは伸縮自在。シリアスにして、どこかファニーな感じが漂う。
そのせいか“死”というテーマを扱いながらも飄々としたムード。余命を諦めた重病の娘も彼女に先立たれたくない母親も鳥の存在に影響され、慌てたり、必死の行動に出たり。そこから生じるドタバタがユーモラス。
不安定な歴史を持つクロアチアで生まれ育ったことで、プスイッチ監督は心の闇に対するユーモアを持ち合わせるようになったというが、軽やかさはそこからくるのだろうか。いずれにしても死そのものは怖くない。怖いのは愛する者を残すこと、または残されることだ。
鳥が、畏怖と一緒に可笑しさも運んで来る
"死"が、オウムに似た鳥の形をしてやってくる。その鳥は、身体のサイズを変え、人間の言葉を話す。人間の身体よりも大きな鳥は、顔を近づけてくるだけで恐ろしいが、手で掴まえられそうなサイズの鳥がラップする姿は、ユーモラスでもある。鳥が、恐怖や畏怖だけでなく、ぼんやりとした可笑しさも漂わせるという佇まいが胸に沁みてくる。
その鳥にどう向き合うのかを、鳥が近づこうとする少女と、その少女を愛する母親、2つの異なる立場から描く。強い母親役を、MCUのヴァル役でお馴染みのジュリア・ルイス=ドレイファスが巧演。本作が初長編となるダイナ・O・プシッチ監督が、ファンタジーとホラーと寓話の狭間をすり抜ける。